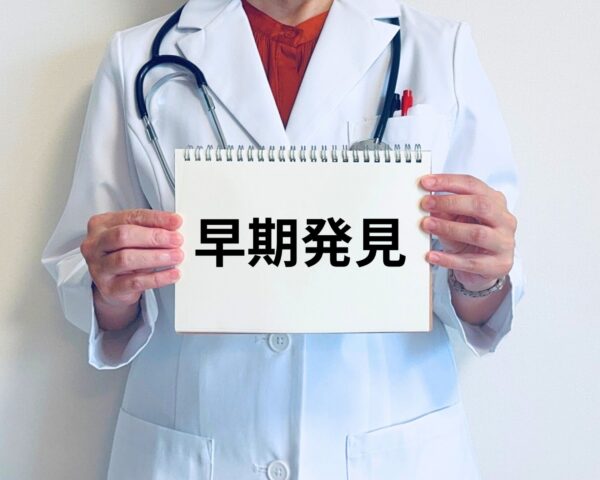目次
過労死とは?定義と実態を知る
過労死とは、長時間労働や強い業務ストレスが原因で、脳・心臓疾患や精神障害を発症し、死亡に至ることを指します。特に日本では、長時間労働が社会問題となっており、厚生労働省が毎年「過労死等防止対策白書」を発表しています。
過労死の主な種類
- 脳・心臓疾患による突然死(心筋梗塞、脳出血、くも膜下出血など)
- 精神疾患による自殺(過労自殺)(うつ病や適応障害の悪化)
厚生労働省によると、過労死の労災認定件数は年間200~300件程度ですが、実際には労災申請されていないケースも多く、潜在的な数はさらに多いと考えられています。

過労死の主な原因|労働環境とメンタルヘルスの関係
過労死の主な原因には、以下のようなものがあります。
長時間労働と過重労働
・法定労働時間を超える残業が常態化
・休日が少なく、休息時間が確保できない
強い業務ストレス
・過度なノルマやプレッシャー
・パワーハラスメントなどの職場環境の悪化
メンタルヘルス不調の放置
・うつ病や適応障害が進行し、自殺のリスクが高まる
・上司や同僚がメンタル不調に気づけない環境
厚生労働省の調査によると、メンタルヘルスの不調を抱える労働者のうち、約60%が何の対策も取らずに働き続けていることが分かっています。これが、最悪のケースでは過労死につながるのです。
過労死について詳しく知りたい方は厚生労働省 「しごとより、いのち。」を参考にしてください
https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/karoushizero/index.html
過労死を防ぐための具体的な対策|企業と個人の取り組み
過労死を防ぐためには、企業と個人の双方が意識を持ち、具体的な対策を講じることが重要です。
企業の対策
✅ 労働時間の適正管理
・36協定の厳守(時間外労働の上限規制)
・勤怠管理システムの導入で労働時間を可視化
✅ メンタルヘルス対策の強化
・ストレスチェック制度の活用
・産業医やカウンセラーの相談窓口を設置
✅ 職場環境の改善
・パワハラ防止研修の実施
・休暇取得の促進(有給休暇・特別休暇の活用)
個人の対策
✅ セルフケアの意識を高める
・定期的に休憩を取り、リラックスする習慣をつける
・心身の不調を感じたら、早めに医師に相談する
✅ 働き方を見直す
・「働きすぎ」のサインに気づく(睡眠不足、イライラ、不安感など)
・転職や異動の選択肢を検討する
産業医面談を活用しましょう!
時間外労働が多くなると企業は従業員に対して産業医面談を提案する必要があります
・社内に窓口を設置
・地域産業保健センターを活用(従業員50人未満の事業所のみ)

特に過労は生活習慣病や精神疾患の増悪が懸念されます。面談内容によって、就業制限、作業の転換を企業に提案することがあります。それでも改善されない場合は「勧告権」を行使することがありますので、企業側は労働者への安全配慮を行いましょう!
労災認定の基準と手続き|過労死が労災認定される条件
過労死が労災認定されるためには、以下の条件を満たす必要があります。
長時間労働による脳・心臓疾患
✅ 発症前1か月間に100時間以上の時間外労働
✅ 発症前2~6か月間に月平均80時間以上の時間外労働
精神障害による過労自殺(労災認定基準)
✅ 業務による強いストレス(パワハラ、極端な業務負荷など)
✅ 精神疾患を発症し、自殺に至ったケース
労災申請は、労働基準監督署に対して申請書を提出することで開始されます。審査には時間がかかることが多いため、専門家(弁護士・社労士)に相談するのも有効です。
まとめ|労働環境の改善で過労死を防ぐためにできること
過労死は、労働環境とメンタルヘルスの悪化が主な原因となる深刻な問題です。企業は労働時間の適正管理やメンタルヘルス対策を強化し、従業員が健康的に働ける環境を作ることが求められます。一方、個人もセルフケアを意識し、異変を感じたら早めに相談することが大切です。
もし労働環境が改善されない場合は、労働基準監督署や専門機関に相談することも選択肢の一つです。過労死を防ぐために、私たち一人ひとりができることを考え、行動していきましょう。
株式会社NoLaBoが提供する産業保健サービス
弊社はメディカルフィットネス事業と産業保健サービスを主軸にし、「健康と運動を通してたくさんの人を幸せにする」ための事業展開をしております。
厚生労働省認定のメディカルフィットネスで医学的な運動食事指導を、産業医、産業看護職、リハ職などが一つのチームとなり顧問先企業をサポートする、日本で唯一の産業保健サービスが行える企業でございます。

略歴
2013年 旭川医科大学医学部医学科卒業、医師免許取得。
脳神経外科学、救急医学をベースに大学での臨床研究や多くの手術症例を経験。
より多くの人を幸せにするため2021年2月、株式会社NoLaBoを設立。
- 2021年8月 エターナルフィット西町南 開業
- 2022年11月 エターナルフィット厚別 開業
- 2024年7月 エターナルフィット円山 開業
- 救急科専門医
- 産業衛生専攻医
- 脳神経外科専門医
- 脳卒中専門医
- 脳血管内治療専門医
- 日本医師会認定健康スポーツ医
- 産業医
- 労働衛生コンサルタント
- 健康経営エキスパートアドバイザー
- 健康運動指導士
- 公認パーソナルトレーナー(NSCA-CSCS/CPT)
~お問い合わせ・資料請求について~
下記ボタンより、お問い合わせ・資料請求ができます。