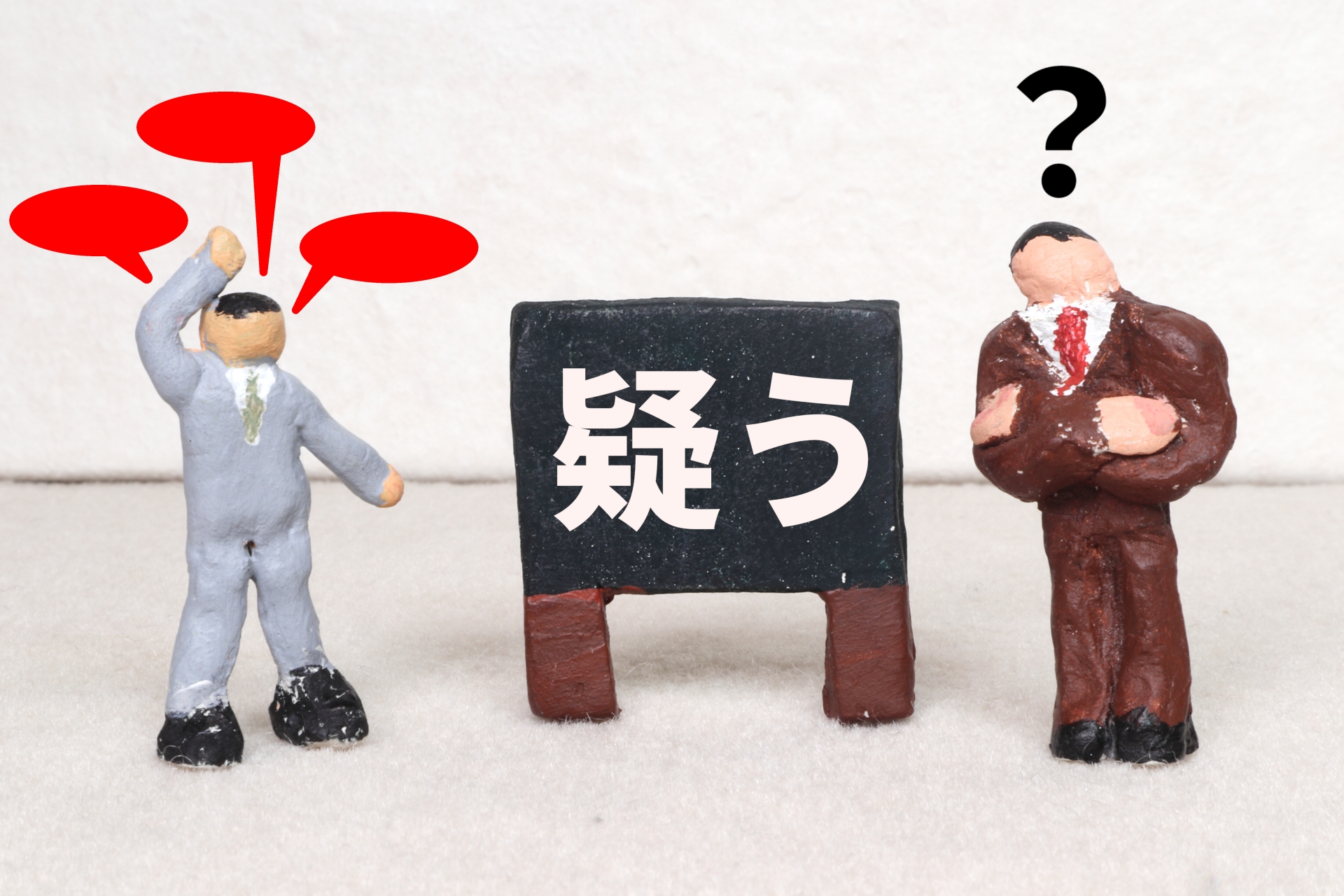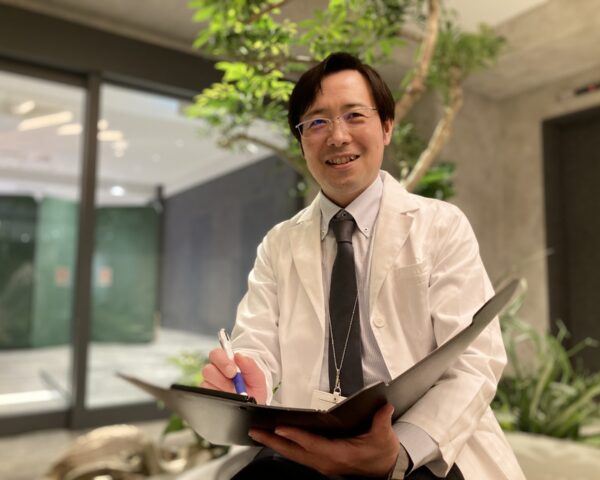目次
産業医制度とは?その役割と目的
産業医とは、職場における労働者の健康管理や衛生管理を担う医師のことを指します。労働安全衛生法により、一定規模以上の企業には産業医の選任が義務付けられており、社員の健康診断の結果に基づくアドバイスや、過重労働・メンタルヘルスに関する面談、職場環境のチェックなどが主な業務です。
本来、産業医は企業と労働者の中立な立場で、労働者の健康と安全を守るための存在です。しかし、現実にはこの「中立性」が形骸化しているという声も少なくありません。
産業医の仕事内容については札幌産業保健サービスのホームページを参考にしてください
なぜ「産業医が信用できない」と言われるのか?
企業寄りの対応
産業医が会社に雇われている立場であるため、社員よりも企業側に立って判断しているように見えるケースがあります。たとえば、過労やストレスの相談をしても「まだ大丈夫」と判断され、配慮がなされないことも。
守秘義務への不安
労働者が面談で話した内容が、本人の同意なく上司に伝わるケースが報告されています。これにより「話せば損をする」と感じる人も少なくありません。
冷たい・機械的な対応
精神的に辛い状況で相談しても、流れ作業のような面談で終わり、共感が得られず、ますます落ち込むケースも。
専門性や人間性の不安
メンタルヘルスや職場環境についての知識が乏しい産業医も存在します。医師であっても「産業医としての適性」は別問題です。
制度への不信感
形だけの面談や、月に数回しか職場に現れないなど、「名ばかり産業医」が実在することで、制度そのものへの疑念が広がっています。
よくあるトラブルと実際の体験談
実際にネット上で報告されているトラブルや私の顧問先の企業が以前顧問にしていた産業医の話を簡単にまとめました。
● 体験談①:「休職を希望したのに、産業医が拒否」
うつ症状が強く、主治医からも休職の勧めがあったが、産業医が「そこまで重くない」と判断し、会社は休職を認めなかった。結果として、症状が悪化し、退職に追い込まれた。
● 体験談②:「相談内容が直属の上司に漏れた」
メンタル不調について相談した翌週、上司から「最近情緒不安定らしいな」と声をかけられた。プライバシーが守られていないと感じ、強い不信感を抱いた。
● 体験談③:「形式的な面談で問題が解決しない」
月に一度の産業医面談があるが、5分程度で終わり、相談しづらく、結局会社の都合に合わせて調整されるだけ。形だけの制度では意味がないと感じた。
信用できる産業医を見分けるポイント
産業医全員が悪いわけではありません。中には、労働者の立場に立って親身に対応してくれる信頼できる産業医もいます。以下のポイントをチェックしましょう。
- 相談内容を丁寧に聞いてくれる
- 本人の同意なしに情報を漏らさないと明言する
- メンタルヘルスや労務の知識が豊富
- 判断や提案の理由を明確に説明してくれる
- 労働者の意見に耳を傾ける姿勢がある
これらの特徴が見られない場合、注意が必要です。自分の健康やキャリアに関わる重要な問題だからこそ、相手を見極める目が求められます。
信用できない産業医を選任し続けるリスク
労働者の健康管理が不十分となり、生産性の低下や休職者の増加を招く
適切な健康管理が行われないと、労働者の健康悪化や業務効率の低下につながります。
労働基準監督署への報告義務違反による罰則
産業医の職務怠慢は、企業が法的義務を果たしていないとみなされ、罰則の対象となる可能性があります。
安全配慮義務違反による訴訟リスク
労働者の健康被害が発生した場合、企業は安全配慮義務違反として訴訟を起こされるリスクがあります。
企業のブランドイメージ悪化による人材確保への影響
健康管理が不十分な企業は、社会的評価が下がり、優秀な人材の確保が難しくなる可能性があります。
信頼できない場合の対処法と相談先
もし「この産業医は信用できない」と感じたら、以下のような対処法があります。
社外の専門機関に相談する
たとえば、労働基準監督署や地域産業保健センター、産業保健総合支援センターなどに相談可能です。労働者が匿名で相談できる窓口もあります。
人事部門に匿名で意見を伝える
会社によっては意見箱や匿名アンケートなどが設けられている場合があります。制度自体の改善につながる可能性もあります。
主治医の意見書を活用する
産業医が信用できない場合、主治医(精神科や心療内科)の診断書や意見書を出して、会社に働きかける方法もあります。
労働組合を活用する
労働組合がある場合は、産業医の対応について報告し、間に入ってもらうことで改善を促すことができます。
まとめ~産業医との関わり方を見直すために~
産業医は本来、私たち労働者の健康を守る立場にある存在ですが、実際にはその機能が十分に果たされていないケースも少なくありません。信用できないと感じたときに我慢するのではなく、外部への相談や会社への働きかけを通じて、状況を改善する手段を知っておくことが大切です。
すべての産業医が悪いわけではなく、信頼できる専門家もいます。だからこそ「声を上げること」「相談すること」を恐れず、自分の健康と働く権利を守るための行動を起こすことが重要です。
株式会社NoLaBoが提供する産業保健サービス
弊社はメディカルフィットネス事業と産業保健サービスを主軸にし、「健康と運動を通してたくさんの人を幸せにする」ための事業展開をしております。
厚生労働省認定のメディカルフィットネスで医学的な運動食事指導を、産業医、産業看護職、リハ職などが一つのチームとなり顧問先企業をサポートする、日本で唯一の産業保健サービスが行える企業でございます。

略歴
2013年 旭川医科大学医学部医学科卒業、医師免許取得。
脳神経外科学、救急医学をベースに大学での臨床研究や多くの手術症例を経験。
より多くの人を幸せにするため2021年2月、株式会社NoLaBoを設立。
- 2021年8月 エターナルフィット西町南 開業
- 2022年11月 エターナルフィット厚別 開業
- 2024年7月 エターナルフィット円山 開業
- 救急科専門医
- 産業衛生専攻医
- 脳神経外科専門医
- 脳卒中専門医
- 脳血管内治療専門医
- 日本医師会認定健康スポーツ医
- 産業医
- 労働衛生コンサルタント
- 健康経営エキスパートアドバイザー
- 健康運動指導士
- 公認パーソナルトレーナー(NSCA-CSCS/CPT)
~お問い合わせ・資料請求について~
下記ボタンより、お問い合わせ・資料請求ができます。