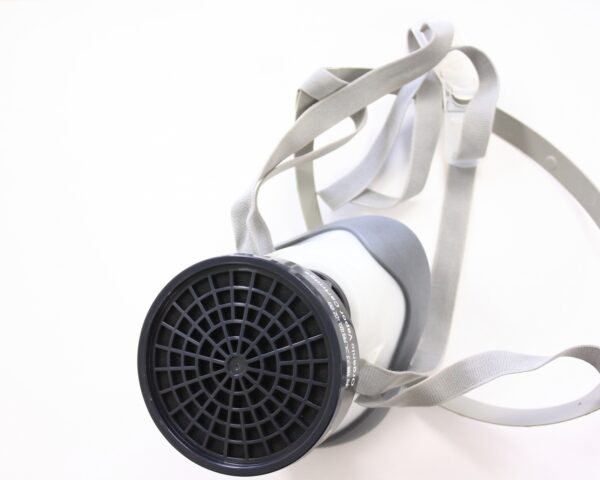アルコール依存症は職場の重要課題
アルコール依存症は個人の問題にとどまらず、職場全体に影響を及ぼす可能性がある疾患です。厚生労働省の調査によると、日本におけるアルコール依存症の疑いがある人は約100万人にのぼるとされています。
企業にとっては、社員の健康管理だけでなく、生産性の低下や職場の安全確保の観点からも重要な課題です。適切な対応を取ることで、社員の回復を支援し、職場環境を健全に保つことができます。
本記事では、企業が取るべきアルコール依存症への対応策や支援方法について解説します。ぜひ最後までご覧ください!
目次
アルコール依存症とは?基礎知識を押さえる
アルコール依存症の定義と特徴
アルコール依存症は、単なる飲酒習慣ではなく、飲酒のコントロールができなくなる病気です。世界保健機関(WHO)の診断基準では、以下のような特徴が挙げられています。
✅ 飲酒量のコントロールが困難
✅ 飲酒をやめると離脱症状(手の震え、不安、発汗など)が出る
✅ 飲酒が最優先になり、仕事や家庭生活が疎かになる
✅ 健康被害(肝機能障害、脳萎縮、うつ病など)が進行する
職場でのアルコール依存症の兆候
職場において、以下のような兆候が見られる場合は、アルコール依存症の可能性を疑う必要があります。
🔹 遅刻や欠勤が増える
🔹 仕事のミスが増加し、集中力が低下する
🔹 アルコールのにおいがすることがある
🔹 休憩時間に飲酒をする、または飲酒後に戻ってくる
🔹 同僚とのトラブルが増える
このような兆候を見逃さず、早期に対応することが重要です。
アルコール依存症について詳しく知りたい方は厚生労働省のホームページを参考にしてください
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000176279.html
企業が取るべき対応策
アルコール依存症のリスクを減らす職場環境づくり
企業としてできる第一歩は、飲酒に寛容な職場文化を見直すことです。
✅ 業務中の飲酒禁止を明確にする(社内ルールの策定)
✅ 過度な飲酒を助長しない(飲み会の強制参加を廃止)
✅ 産業医や保健師と連携し、健康相談の場を設ける
アルコール依存症の疑いがある社員への対応
社員の飲酒問題が発覚した場合、企業はどのように対応すべきでしょうか?
📌 ステップ1:状況を把握する
・直属の上司や人事担当者が本人と話し合い、飲酒の実態や健康状態を確認する
・感情的にならず、冷静に話を聞く姿勢を持つ
📌 ステップ2:専門家と連携する
・産業医や保健師と相談し、医療機関への受診を促す
・社内にEAP(従業員支援プログラム)があれば活用する
📌 ステップ3:就業上の対応を検討する
・業務への影響を評価し、配置転換や休職の検討を行う
・リハビリ後の復職支援プログラムを準備する
アルコール依存症からの回復を支援する
企業が提供できる支援策
アルコール依存症は「意志の弱さ」ではなく「病気」です。回復には、適切な治療と職場の支援が不可欠です。
🔹 医療機関の受診をサポートする(診療情報の提供、通院への配慮)
🔹 社内カウンセリングの活用(ストレス管理の指導)
🔹 復職プログラムの導入(段階的な業務復帰の支援)
社員の回復を後押しする職場環境
回復した社員がスムーズに職場復帰できるよう、以下のような環境を整えることが重要です。
✅ 偏見や差別を防ぐため、社員教育を実施する
✅ 復職後も定期的なフォローを行い、メンタル面をサポートする
✅ 再発防止のため、飲酒を控える環境を整える(社内の飲酒ルールを厳格化)
企業がこれらの対応を行うことで、社員の健康と生産性を守ることができるのです。
まとめ:企業としての責任と今後の課題
アルコール依存症は、単なる「飲みすぎ」ではなく、深刻な健康問題であり、職場全体に影響を及ぼす可能性のある病気です。
企業がすべきことは、①予防策を講じる、②問題が発生した際に適切に対応する、③回復を支援することです。
🔹 飲酒リスクを抑える職場環境を整える
🔹 産業医・保健師と連携し、早期発見・早期対応を行う
🔹 回復後の復職支援を充実させる
アルコール依存症の社員を適切に支援することは、企業にとってもプラスになります。社員の健康を守ることは、結果的に生産性の向上や職場環境の改善につながるため、積極的な取り組みが求められます。
企業全体で適切な知識を持ち、支援体制を整えることが、健全な職場づくりへの第一歩となるでしょう。
株式会社NoLaBoが提供する産業保健サービス
弊社はメディカルフィットネス事業と産業保健サービスを主軸にし、「健康と運動を通してたくさんの人を幸せにする」ための事業展開をしております。
厚生労働省認定のメディカルフィットネスで医学的な運動食事指導を、産業医、産業看護職、リハ職などが一つのチームとなり顧問先企業をサポートする、日本で唯一の産業保健サービスが行える企業でございます。

略歴
2013年 旭川医科大学医学部医学科卒業、医師免許取得。
脳神経外科学、救急医学をベースに大学での臨床研究や多くの手術症例を経験。
より多くの人を幸せにするため2021年2月、株式会社NoLaBoを設立。
- 2021年8月 エターナルフィット西町南 開業
- 2022年11月 エターナルフィット厚別 開業
- 2024年7月 エターナルフィット円山 開業
- 救急科専門医
- 産業衛生専攻医
- 脳神経外科専門医
- 脳卒中専門医
- 脳血管内治療専門医
- 日本医師会認定健康スポーツ医
- 産業医
- 労働衛生コンサルタント
- 健康経営エキスパートアドバイザー
- 健康運動指導士
- 公認パーソナルトレーナー(NSCA-CSCS/CPT)
~お問い合わせ・資料請求について~
下記ボタンより、お問い合わせ・資料請求ができます。