現代社会では、デスクワーク中心の職場環境が増え、運動不足やストレスによる肥満が深刻な問題となっています。肥満は従業員の健康を損なうだけでなく、企業の生産性や医療コストにも影響を及ぼします。本記事では、「職場における肥満対策と減量支援プログラム」の重要性を解説し、具体的な施策を紹介します。ぜひ最後までご覧ください!
目次
職場における肥満の現状とリスク
日本における職場の肥満率
厚生労働省のデータによると、日本の成人の約30%がBMI25以上の「肥満」に分類されます。特に、40〜50代の働き盛り世代の男性では約40%が肥満であるという統計があります。
この傾向は、デスクワークの増加、長時間労働、不規則な食生活、運動不足が要因となっています。また、企業によっては健康診断の結果に基づくフォローアップが不十分であり、生活習慣の改善が進まないケースも多いです。
肥満が引き起こす健康リスク
肥満は以下のような健康リスクを引き起こします。
メンタルヘルスへの悪影響(ストレス、不安、うつ病など)
生活習慣病のリスク増大(糖尿病、高血圧、脂質異常症など)
心血管疾患の発症リスク上昇(心筋梗塞、脳卒中など)
筋骨格系への負担増(腰痛、関節痛など)
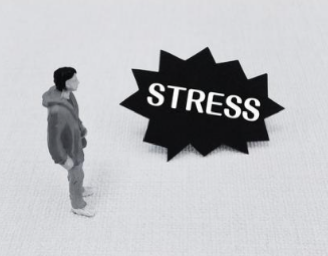
これらの健康リスクは、労働生産性の低下、欠勤・休職の増加、医療費負担の増大といった形で企業の経営にも影響を及ぼします。
職場環境が肥満に及ぼす影響
デスクワーク中心の働き方
現代の職場では、座りっぱなしの時間が長く、運動する機会が少ないことが肥満の一因となっています。研究によると、1日6時間以上座っている人は、肥満や糖尿病のリスクが高まるとされています。
社内食堂やコンビニの食事選択
社内の食堂やコンビニの食事が高カロリー・高脂質に偏っていると、従業員の肥満リスクが高まります。特に、揚げ物や炭水化物中心の食事、甘い飲料の摂取が習慣化している職場では、健康管理が難しくなります。
ストレスと肥満の関係
長時間労働や業務のプレッシャーがストレスを引き起こし、過食や暴飲暴食の原因になります。特に、ストレスによるコルチゾールの増加は内臓脂肪の蓄積を促進し、肥満につながります。
生活習慣病や肥満症の治療は食事療法と運動療法で良くなりますが、必要に応じて処方することがあります。グッドライフクリニックのホームページに詳しい記事が書かれてますので参考にしてください。
効果的な減量支援プログラムの構築方法
企業ができる具体的な施策
企業が職場で肥満対策を進めるためには、以下のような施策が有効です。
健康診断データの活用と個別指導
健康診断の結果を活用し、BMIや内臓脂肪率に応じた個別の健康指導を実施することで、肥満の進行を防ぐことができます。

社内ウォーキング・フィットネスプログラムの導入
朝や昼休みに行う簡単なストレッチやヨガ
1日8,000歩以上を目標にしたウォーキングキャンペーン
オフィス内での立ち仕事スペースやスタンディングデスクの導入

社食や飲食補助の健康的な選択肢を増やす
「ヘルシーランチ」の補助金制度を導入する
野菜やたんぱく質中心のメニューを充実させる
ジュースや炭酸飲料の代わりに水やお茶を提供する

メンタルヘルスケアとストレス管理
仕事とプライベートのバランスを考慮した働き方改革
定期的なストレスチェック
産業医やカウンセラーによるメンタルヘルス相談

成功事例と企業が取り組むべき具体策
企業の成功事例
① A社(IT企業)
- 社内に「ウォーキングミーティング」を導入し、1日30分以上歩く時間を確保
- 食堂でのカロリー表示を義務化し、健康的な食事を推奨
② B社(製造業)
- 社員向けの減量プログラムを実施し、6ヶ月で平均2kgの減量を達成
- トレーナーによる運動指導を社内で実施
企業が継続的に取り組むべきこと
- トップダウンで健康経営を推進する(経営層の理解が重要)
- 健康プログラムの効果測定を定期的に実施する
- 従業員が自主的に参加できる仕組みを作る
まとめ:企業と従業員が共に健康を目指すために
職場における肥満対策は、従業員の健康維持だけでなく、企業の生産性向上や医療費削減にも直結する重要な課題です。食事、運動、メンタルケアといった多角的なアプローチを取り入れ、企業全体で健康経営を推進することが求められます。
今後、企業が積極的に減量支援プログラムを導入することで、従業員の健康意識も高まり、より良い職場環境が生まれるでしょう。
まずは小さなことからでも実践し、職場全体で健康づくりを始めてみませんか?
株式会社NoLaBoが提供する産業保健サービス
弊社はメディカルフィットネス事業と産業保健サービスを主軸にし、「健康と運動を通してたくさんの人を幸せにする」ための事業展開をしております。
厚生労働省認定のメディカルフィットネスで医学的な運動食事指導を、産業医、産業看護職、リハ職などが一つのチームとなり顧問先企業をサポートする、日本で唯一の産業保健サービスが行える企業でございます。

略歴
2013年 旭川医科大学医学部医学科卒業、医師免許取得。
脳神経外科学、救急医学をベースに大学での臨床研究や多くの手術症例を経験。
より多くの人を幸せにするため2021年2月、株式会社NoLaBoを設立。
- 2021年8月 エターナルフィット西町南 開業
- 2022年11月 エターナルフィット厚別 開業
- 2024年7月 エターナルフィット円山 開業
- 救急科専門医
- 産業衛生専攻医
- 脳神経外科専門医
- 脳卒中専門医
- 脳血管内治療専門医
- 日本医師会認定健康スポーツ医
- 産業医
- 労働衛生コンサルタント
- 健康経営エキスパートアドバイザー
- 健康運動指導士
- 公認パーソナルトレーナー(NSCA-CSCS/CPT)
~お問い合わせ・資料請求について~
下記ボタンより、お問い合わせ・資料請求ができます。


