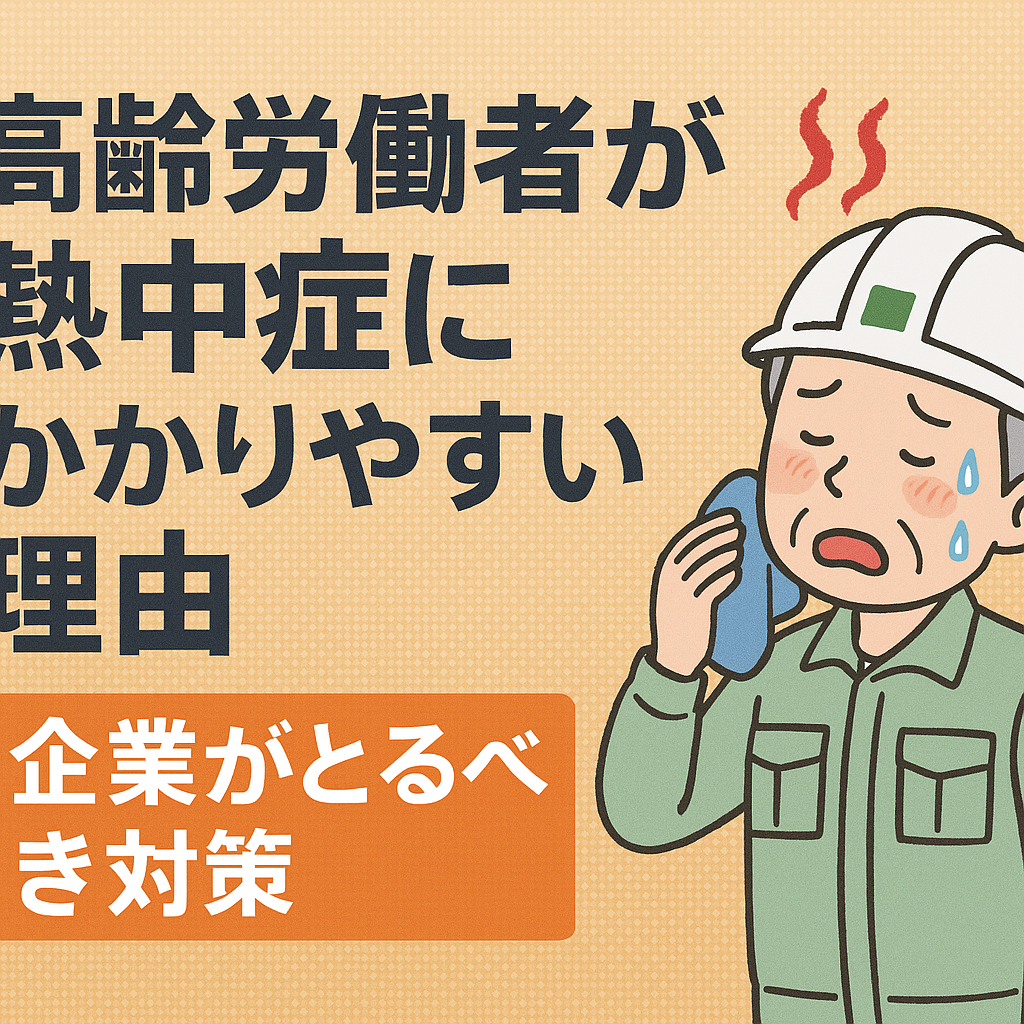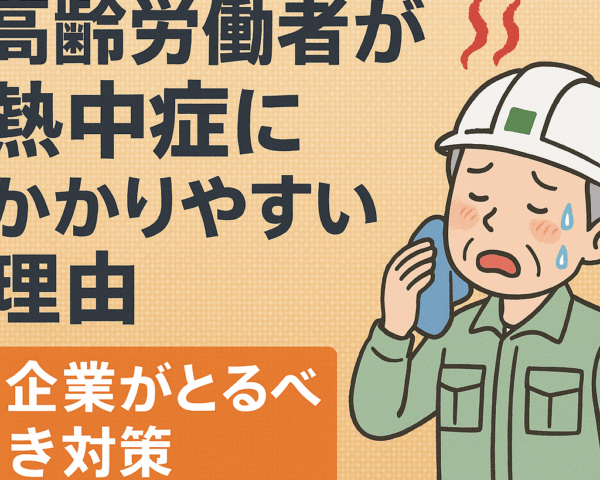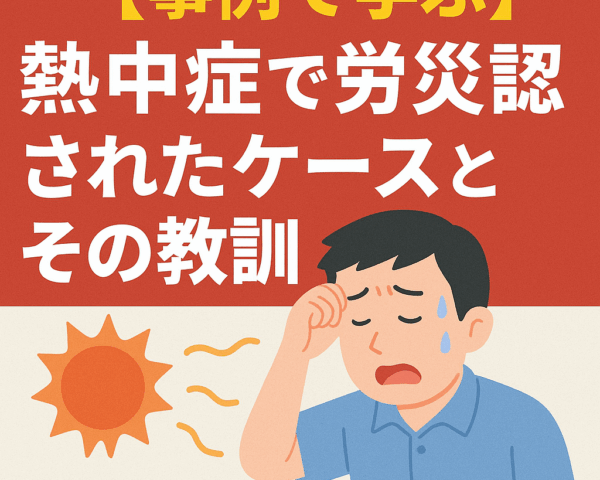「最近、職場で高齢の方が体調を崩して倒れたらしい」
「猛暑の中での作業、大丈夫だろうか…」
「熱中症って、若い人よりも高齢者の方が重症化しやすいって本当?」
こんな声が、現場のあちこちで聞こえるようになってきました。
かつては「夏でも涼しい」と言われていた北海道。しかし近年では、札幌市内でも真夏日が続き、30℃を超える日が珍しくありません。特に現場作業や屋外業務に従事する高齢の労働者にとって、熱中症のリスクは年々高まっています。
今回は、株式会社NoLaBoの札幌産業保健サービスより、産業医の立場から「高齢労働者が熱中症にかかりやすい理由と企業がとるべき対策」について詳しく解説します。
高齢労働者を守るために、企業や現場が今すぐ取り組むべき具体的な対策を、ぜひこの機会にご確認ください。
目次
高齢労働者が熱中症にかかりやすい理由
①感覚機能の低下と気づきの鈍化
加齢により皮膚表面の温度センサーが減少し、暑さや脱水に対する感覚が鈍くなります。そのため、「暑い」「のどが渇いた」と感じにくく、気づいたときにはすでに体温が上昇しているケースが多いです
②体温調節機能の低下
高齢になると汗線の数や発汗量が減少し、血管の皮膚への拡張反応も低下します。その結果、熱を逃がしにくく、体温が高止まりしやすい傾向があります
③体内水分量・塩分調整機能の低下
体液貯留が減り、脱水状態に陥りやすい体質となります。また、腎機能の低下もあり、体液の再吸収や塩分保持がうまくできません 。
④熱中症の進行が速い
自律神経の応答が遅く、身体の冷却反応開始までに時間がかかるため、体温上昇が早く、重症化しやすくなります 。
企業が講ずべき基本対策
2025年6月1日より、熱中症対策は労働安全衛生規則の改正で義務化されました。企業は以下の3点を整備し、従業員へ周知する必要があります
- 熱中症発生時の報告体制とマニュアル
- 悪化防止の措置準備(冷却、搬送、休憩などの具体的行動)
- 職場環境整備および教育の実施
これらは社内の安全配慮義務にも直結しており、未履行の場合には罰則や労災責任となる可能性があります
高齢労働者に特化した企業対策
以下は高齢者特有のリスクを踏まえた対策です。
①作業前簡易問診・体調チェック
- 前夜睡眠・朝食・服薬内容の確認などを簡易問診表で実施。
- 朝礼や巡視時に、体調や表情、発汗などを毎回観察・記録。
②暑熱順化プログラム
- 5月~6月の期間で、初日は30分軽作業から開始し、徐々に作業時間を延ばす
- これにより汗腺や体温調節システムが順次適応し、猛暑期(7・8月)への備えが可能。
③作業環境と装備の整備
④水分・塩分の管理体制
- 通常の水ではなく、ナトリウム入りスポーツドリンクや経口補水液を活用。
- 定時アラーム・放送で補給を励行、飲水記録をチェックシートで管理。
⑤見守り体制とバディ制度
⑥作業スケジューリング
応急対応プロトコルと教育
①応急処置手順の明文化と訓練
- マニュアルには、涼しい場所への移動、水分・塩分補給、冷却処置、119通報基準を記述し、現場に常掲示。
- 定期的な訓練(模擬通報・応急処置)で実動力を強化。
②熱中症教育の実施
- 全社員に対し、熱中症のメカニズム・重症徴候・予防法・応急処置を教育。
- 高齢者には特に重点を置き、「暑さに気づきにくい」「のどの渇きに気づかない」などを明示。
制度・制度支援・補助金の活用
厚労省の補助制度活用
- 「令和7年度エイジフレンドリー補助金」では、高年齢労働者の災害防止設備導入や熱中症対策経費に対する補助あり(上限100万円)。
- 送風機、冷却ベスト、見守りカメラ等の導入時に活用を検討。
外部専門家の活用
- 産業医や労働衛生コンサルタントと連携し、リスク評価や対策検討を行うことが有効。
- 継続的な指導体制によって、制度上の義務・安全配慮義務を確実に履行。
まとめ ~高齢者を守るための「きめ細かさ」を~
| リスク要因 | 対応施策 | 効果 |
| 感覚鈍化 | 問診・巡視バディ制度 | 早期異変の把握 |
| 体温調節機能低下 | 暑熱順化・環境整備 | 熱負荷の軽減 |
| 脱水しやすい | 塩分入り飲料・管理 | 循環維持と疲労軽減 |
| 法令義務 | マニュアル・報告体制 | 企業責任の履行 |
| 緊急対応力 | 教育・訓練 | 重症化防止 |
高齢労働者は身体的に熱中症のリスクが高いだけでなく、症状が気づきにくく重症化しやすいため、企業としては“きめ細かく・多層的に”対策を講じる責任があります。体調チェック、作業時間管理、環境整備、教育・マニュアル、応急体制、補助制度の活用…すべてを連動させることで、安全で働きやすい環境を実現できます。
産業医の視点から
- 毎日の人体変化に寄り添い、声掛けと観察を習慣化
- 法改正に対応した文書・マニュアルの整備
- 補助金・専門家活用による実効性のある設備導入
- 定期的な教育・訓練による現場への浸透と実践確保
これらを通じて「高齢者だから仕方ない」ではなく、「高齢者だからこそ、企業が支える」を実現しましょう。
株式会社NoLaBoが提供する産業保健サービス
弊社はメディカルフィットネス事業と産業保健サービスを主軸にし、「健康と運動を通してたくさんの人を幸せにする」ための事業展開をしております。
厚生労働省認定のメディカルフィットネスで医学的な運動食事指導を、産業医、産業看護職、リハ職などが一つのチームとなり顧問先企業をサポートする、日本で唯一の産業保健サービスが行える企業でございます。

略歴
2013年 旭川医科大学医学部医学科卒業、医師免許取得。
脳神経外科学、救急医学をベースに大学での臨床研究や多くの手術症例を経験。
より多くの人を幸せにするため2021年2月、株式会社NoLaBoを設立。
- 2021年8月 エターナルフィット西町南 開業
- 2022年11月 エターナルフィット厚別 開業
- 2024年7月 エターナルフィット円山 開業
- 救急科専門医
- 産業衛生専攻医
- 脳神経外科専門医
- 脳卒中専門医
- 脳血管内治療専門医
- 日本医師会認定健康スポーツ医
- 産業医
- 労働衛生コンサルタント
- 健康経営エキスパートアドバイザー
- 健康運動指導士
- 公認パーソナルトレーナー(NSCA-CSCS/CPT)
~お問い合わせ・資料請求について~
下記ボタンより、お問い合わせ・資料請求ができます。