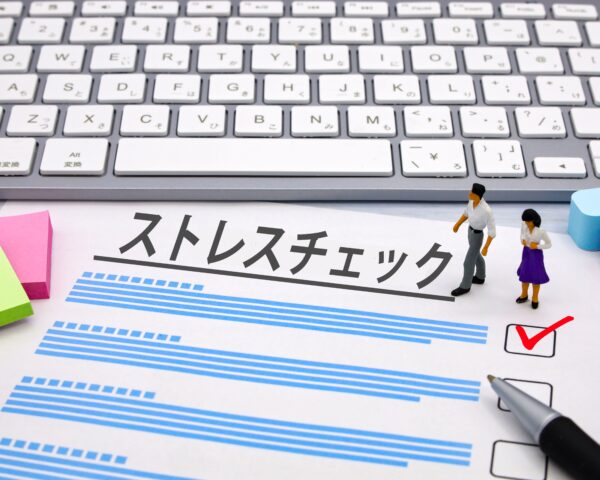目次
ストレスチェック制度とは?
2015年12月から義務化された「ストレスチェック制度」。これは、労働者が自らのストレス状況に気づき、メンタルヘルス不調を未然に防ぐことを目的とした一次予防のための仕組みです。50人以上の労働者がいる事業所では、年1回の実施が義務づけられています。
しかしながら、多くの職場ではこの制度に対する誤解や誤った運用が存在し、制度が本来の役割を果たせていないという声も少なくありません。
今回は、そんな「ストレスチェック制度」に関するよくある誤解5つを紹介し、それぞれについて正しい知識と対応方法を解説します。職場全体で正しく理解し、健康経営を実現する第一歩にしましょう。
誤解①:ストレスチェックは病気の診断ツール
❌ よくある誤解
「ストレスチェックを受けたら病名がつくのでは?」「精神疾患があると判定されるのが怖い」といった声はよく聞かれます。特にメンタル不調に敏感な方にとっては、自分の状況が“診断”されるような印象を持ってしまいがちです。
✅ 正しい理解
ストレスチェックはあくまで「気づき」のためのツールであり、医療診断ではありません。これは、病気の有無を判断するものではなく、自分のストレス状態の目安を知るための調査です。
厚生労働省のガイドラインでも、ストレスチェックは「一次予防」であり、診断を目的としたものではないことが明記されています。
誤解②:結果が上司や人事に筒抜けになる
❌ よくある誤解
「ストレスチェックの結果が人事に渡って、評価や昇進に影響するのでは?」という不安もよく聞きます。特に高ストレスと判定された場合、不利益を被るのではと感じる社員も少なくありません。
✅ 正しい理解
ストレスチェックの結果は、本人の同意がない限り第三者(上司・人事など)に開示されません。実際に結果を確認できるのは、本人と実施者(産業医等)、実施事務従事者のみです。
さらに、結果の扱いについては「労働者の不利益な取り扱いをしてはならない」と法律で明確に禁止されています。
誤解③:社内ではストレスチェック結果を扱えない
❌ よくある誤解
「個人情報だから、社内の誰も触れてはいけない」「外部委託しないとダメなのでは?」と考える企業もあります。
✅ 正しい理解
社内でも、産業医や実施事務従事者であればストレスチェックの結果を取り扱うことが可能です。ただし、これらの担当者には守秘義務が課されており、不適切に共有することは法律違反となります。
つまり、必要な範囲であれば社内でも対応可能であり、逆に適切な体制を整えることが企業責任といえます。
誤解④:高ストレス者には社内から接触できない
❌ よくある誤解
「ストレスが高い人に声をかけるとハラスメントになるのでは?」「何もしない方がいい」と思い込む管理職もいます。
✅ 正しい理解
高ストレス者には、産業医や実施事務従事者が適切に声をかけたり、面接指導の案内をしたりすることができます。むしろ、放置する方がリスクが高まります。
もちろん、本人の意思を尊重しながら、丁寧にアプローチすることが重要です。会社側も、対応マニュアルを整備しておくことで安心して対応できます。
誤解⑤:面接指導は完全に秘匿される
❌ よくある誤解
「面接指導を申し出ても、それが会社に知られることはない」という誤解も見られます。
✅ 正しい理解
面接指導を申し出ると、その時点で結果が会社(上司・人事)に開示されることに同意したとみなされます。そして、産業医が「配慮が必要」と判断した場合は、その意見が会社に共有されます。
重要なのは、そのプロセスを事前に周知し、本人の納得を得てから進めることです。相談窓口やガイドラインでの明確化が、信頼構築につながります。
制度の誤解が生まれる背景と防止策
ストレスチェック制度に関する誤解は、制度そのものの専門用語の多さや、社内での運用ルールの不透明さに起因しています。また、制度を「形だけ」で運用してしまうと、社員側に不信感が生まれやすくなります。
誤解を防ぐためのポイント
- 制度の目的とルールを明文化して社内に周知
- 集団分析を活用し、職場改善につなげる
- 面接指導の意義を説明し、安心して申し出できる体制を整える
- 守秘義務を徹底し、担当者の教育を行う
これらの施策が、「信頼できる制度運用」の基盤となります。
まとめ ~正しい理解が職場のメンタルヘルスを守る~
ストレスチェックは「診断」ではなく、「予防」のための大切な制度です。正しい知識で誤解を防ぎ、職場全体で安心して活用できる仕組みを整えることが、健康経営への第一歩となります。
株式会社NoLaBoが提供する産業保健サービス
弊社はメディカルフィットネス事業と産業保健サービスを主軸にし、「健康と運動を通してたくさんの人を幸せにする」ための事業展開をしております。
厚生労働省認定のメディカルフィットネスで医学的な運動食事指導を、産業医、産業看護職、リハ職などが一つのチームとなり顧問先企業をサポートする、日本で唯一の産業保健サービスが行える企業でございます。

略歴
2013年 旭川医科大学医学部医学科卒業、医師免許取得。
脳神経外科学、救急医学をベースに大学での臨床研究や多くの手術症例を経験。
より多くの人を幸せにするため2021年2月、株式会社NoLaBoを設立。
- 2021年8月 エターナルフィット西町南 開業
- 2022年11月 エターナルフィット厚別 開業
- 2024年7月 エターナルフィット円山 開業
- 救急科専門医
- 産業衛生専攻医
- 脳神経外科専門医
- 脳卒中専門医
- 脳血管内治療専門医
- 日本医師会認定健康スポーツ医
- 産業医
- 労働衛生コンサルタント
- 健康経営エキスパートアドバイザー
- 健康運動指導士
- 公認パーソナルトレーナー(NSCA-CSCS/CPT)
~お問い合わせ・資料請求について~
下記ボタンより、お問い合わせ・資料請求ができます。