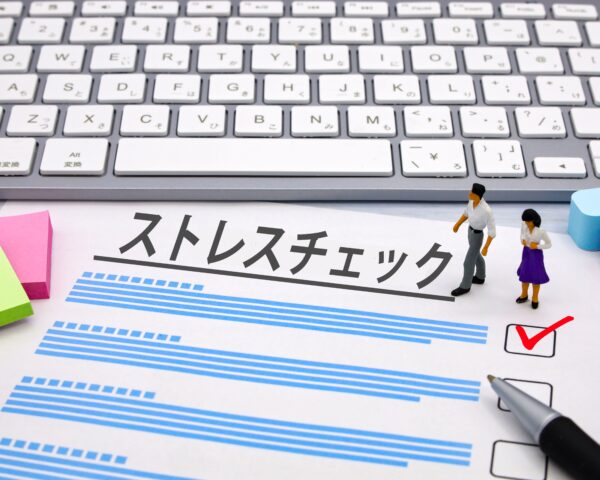目次
ストレスチェック制度とは?目的と義務の背景
ストレスチェック制度は、2015年12月に労働安全衛生法の改正によって義務化された取り組みで、従業員数50人以上の事業場に対して、毎年1回のストレスチェックの実施が義務付けられています。
その目的は以下の3点に集約されます
- 従業員のメンタルヘルスの不調を未然に防ぐこと
- 高ストレス者を早期に把握し、必要な支援につなげること
- 組織全体のストレス状況を把握し、職場環境改善につなげること
ストレスチェックは、単なる「健康調査」ではなく、企業にとっては職場改善や離職防止、労災リスクの軽減などにつながる極めて重要な取り組みです。
では、この制度を「どのように実施するか」という選択肢には大きく2つあります。
- 内製(社内で実施)
- 外部委託(専門業者に任せる)
それぞれの特徴と、メリット・デメリットを比較していきましょう。
ストレスチェックを「内製」で実施するメリット・デメリット
内製のメリット
- 柔軟な対応が可能
社内の状況や業務内容に応じた、カスタマイズされた運用がしやすく、実態に合ったストレスチェックが行えます。 - コストを抑えやすい
すでに産業医や保健スタッフが在籍していれば、新たな外注費用が不要なため、コストを最小限に抑えられることがあります。 - 社内との連携がスムーズ
日々のやり取りを行っている人事部門や管理職と密に連携でき、迅速な対応が可能になります。
内製のデメリット
- 人的リソースが必要
設問設計・実施・回収・分析・報告など多くの工数が必要で、特に人事部門や産業医に負担が集中します。 - プライバシー懸念による回答精度の低下
「社内で見られるのでは?」という懸念から、従業員が本音を答えにくくなる可能性があります。 - 制度設計が不十分になりやすい
厚労省の指針に沿った形で設問を組んだり、高ストレス者への対応フローを整えるには専門知識が必要です。
ストレスチェックを「外部委託」するメリット・デメリット
外部委託のメリット
- 専門的・効率的な実施が可能
ストレスチェック専門業者は、設問設計・集計・分析・報告書の作成までワンストップで対応してくれます。 - プライバシー保護の信頼性が高い
第三者機関が介在することで、従業員が安心して本音で回答できる環境が整い、データの精度が高まります。 - 最新の知見に基づいた支援が受けられる
産業医・精神科医と連携している企業も多く、専門的なアドバイスや職場改善の提案が受けられる点も魅力です。 - 法律対応やリスク管理が万全
労働安全衛生法への準拠、報告義務の対応、万一の労災対応など、法的リスクをカバーしてくれます。
外部委託のデメリット
- コストが発生する
外部業者に委託するため、規模やサービス内容によっては数十万円以上の費用が発生します。 - 社内との連携が不可欠
業者任せにしてしまうと、職場の実情が反映されないストレスチェックになるリスクがあります。 - 業者選定の手間と比較検討が必要
信頼できる業者を選ぶためには、実績・価格・サービス内容を比較しなければなりません。
外部委託と内製、どちらを選ぶべき?判断のポイント
では、自社では「外部委託」と「内製」どちらを選ぶべきか、判断する際の主なポイントを整理してみましょう。
| 判断基準 | 内製が適している場合 | 外部委託が適している場合 |
| 人的リソース | 産業医や保健師が常駐している | 専任スタッフが不足している |
| コスト | 業務を自社で賄いたい | 投資対効果を重視する |
| プライバシー | 社内文化的に信頼がある | 情報保護が特に重要 |
| 制度設計の知見 | 社内に専門家がいる | 専門的な設計が必要 |
| 規模 | 小規模事業場 | 中~大規模事業場 |
多くの企業では、「第1回は外部委託で実施し、知見とノウハウを蓄積した後に内製に切り替える」というハイブリッド型の運用を選ぶケースもあります。
専門家の視点から見るおすすめの実施体制とは
産業医や労働衛生コンサルタントとして現場を多数見てきた経験から言えば、以下の観点を重視することをおすすめします。
- 従業員のプライバシー保護を最優先に考える
- 初回は外部委託で制度設計の基盤を作る
- フォローアップ体制まで一体で構築する
- 費用対効果を中長期的に判断する
特に「本音を引き出す」「分析結果を有効活用する」という観点では、専門的な支援が不可欠です。外部委託を検討することで、制度としての完成度が格段に上がります。
まとめ
ストレスチェック制度の運用方法は、「内製」も「外部委託」も一長一短があります。大切なのは、自社の体制や目的、従業員の状況に応じて最適な方法を選ぶことです。
| 項目 | 内製 | 外部委託 |
| 柔軟性 | 高い | やや低いが標準化されている |
| コスト | 低め(ただし隠れた人件費あり) | 中〜高 |
| 精度 | 社内事情に左右される | 高精度なデータ取得が可能 |
| プライバシー | 懸念あり | 信頼性が高い |
従業員のメンタルヘルスを守るという観点では、専門性・信頼性・継続性が求められます。その意味で、外部委託は非常に有効な選択肢となるでしょう。
株式会社NoLaBoが提供する産業保健サービス
弊社はメディカルフィットネス事業と産業保健サービスを主軸にし、「健康と運動を通してたくさんの人を幸せにする」ための事業展開をしております。
厚生労働省認定のメディカルフィットネスで医学的な運動食事指導を、産業医、産業看護職、リハ職などが一つのチームとなり顧問先企業をサポートする、日本で唯一の産業保健サービスが行える企業でございます。

略歴
2013年 旭川医科大学医学部医学科卒業、医師免許取得。
脳神経外科学、救急医学をベースに大学での臨床研究や多くの手術症例を経験。
より多くの人を幸せにするため2021年2月、株式会社NoLaBoを設立。
- 2021年8月 エターナルフィット西町南 開業
- 2022年11月 エターナルフィット厚別 開業
- 2024年7月 エターナルフィット円山 開業
- 救急科専門医
- 産業衛生専攻医
- 脳神経外科専門医
- 脳卒中専門医
- 脳血管内治療専門医
- 日本医師会認定健康スポーツ医
- 産業医
- 労働衛生コンサルタント
- 健康経営エキスパートアドバイザー
- 健康運動指導士
- 公認パーソナルトレーナー(NSCA-CSCS/CPT)
~お問い合わせ・資料請求について~
下記ボタンより、お問い合わせ・資料請求ができます。