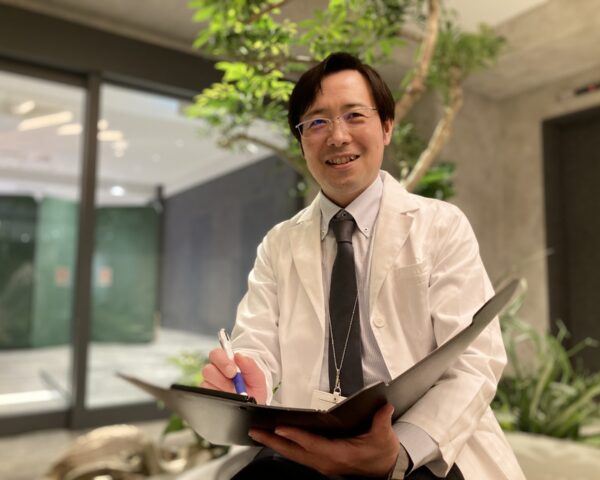ストレスチェックで高ストレス者になると、産業医面談を行うことが勧められます。それは面談を行うことで、精神科疾患が隠れてないか、高ストレスになる原因が解決できるものなのか、などを事前情報と面談の中で判断する必要があります。2025年3月に従業員50人未満の事業所でもストレスチェックが義務化となる発表がされ、今後中小企業だけではなく、小規模事業所にも産業医の介入が必要になるケースが増えてくると予想されます。
そんな中、産業医面接が意味がないという話を耳にすることがあります。なぜそのように思われてしまうのかを現役産業医が解説します。ぜひ最後までご覧ください!
目次
産業医面談とは?目的と制度の背景
産業医面談とは、従業員の健康を守るために設けられた制度の一つで、特に長時間労働者やメンタル不調を訴える社員を対象に実施されます。企業は労働安全衛生法に基づき、一定の条件を満たす従業員に対して産業医による面談を行う義務があります。
目的は主に以下の3点です。
- 心身の健康チェックと相談機会の提供
- 労働環境や勤務時間の見直し提案
- 企業による健康リスクマネジメント
しかし、制度としては整っている一方で、現場での「実感」として「意味ない」と感じる声も少なくありません。
「意味ない」と言われる理由5つの本音
形式的すぎる対応
「とりあえず面談した」という記録を残すだけの形骸化した運用が多く、実質的な効果が見えにくいと感じる人が多いです。
相談しづらい雰囲気
産業医が会社側の人間に見える場合、従業員は本音を話しにくく、「本当のことを言ったら評価に響くのでは?」と不安になるケースがあります。
面談後の変化がない
相談しても、職場環境や業務内容に変化がなければ「意味なかった」と感じるのは当然です。アクションが伴わないことが問題視されています。
そもそも時間が短すぎる
10~15分程度の短い面談では、深い話ができないことも。慌ただしく終わる面談では信頼関係を築くのも難しいです。
専門外の対応力不足
メンタル面の相談でも、産業医によっては専門知識が不十分で、精神科医のような対応ができないこともあります。
実は使い方次第?産業医面談を有効活用する方法
実際には、産業医面談をうまく活用している人もいます。ポイントは以下の通りです。
- 準備をすること:事前に話したい内容、要望、悩みを整理しておくことで短い時間でも的確に伝えられます。
- 記録に残ることを活用:面談は記録されるため、「この状況を会社に伝えた証拠」として活用することもできます。
- 信頼できる産業医を見つける:継続的な関係性が築けると、面談の質も高まります。
また、産業医によっては親身になってくれる人も多く、「最初は期待してなかったけど、相談してよかった」という声もあります。
面談後の対応がポイント!企業と産業医の本音事情
産業医面談で重要なのは、実はその後の企業の対応です。相談内容を受けて、上司や人事がどう動くかによって、面談の価値は大きく変わります。
しかし、現実には「相談したのに放置」「改善案が反映されない」などのケースも多く、従業員側の不信感が募ります。一方で、企業側も「制度としての対応」に追われ、実務として十分な時間やリソースを割けていないという事情もあります。
また、産業医自身も中立的立場を維持する難しさに悩んでいることが多く、「従業員の味方になりたいが、企業側にも配慮が必要」というジレンマを抱えているのが実情です。
産業医面談は変わるべき?今後の制度への期待と提案
今後、産業医面談がより「意味のあるもの」になるためには、以下のような改革が求められます。
- 産業医の質とスキルの向上
- 企業による本気のフォロー体制
- 従業員の声を反映する仕組み
- 匿名相談や第三者機関との連携強化
産業医面談は、うまく機能すれば「心の健康を守る砦」となり得ます。制度を形だけのものにしないために、企業・産業医・従業員の三者が「本音」で向き合う仕組みが必要です。
まとめ
「産業医面談は意味ない」と感じる声には、形式的な対応や実効性のなさ、信頼関係の欠如といった背景があります。しかし、準備や活用次第で本来の目的である「従業員の健康支援」に役立てることも可能です。今後は、制度の本質を見直し、より実効性のある面談体制への改革が求められています。
株式会社NoLaBoが提供する産業保健サービス
弊社はメディカルフィットネス事業と産業保健サービスを主軸にし、「健康と運動を通してたくさんの人を幸せにする」ための事業展開をしております。
厚生労働省認定のメディカルフィットネスで医学的な運動食事指導を、産業医、産業看護職、リハ職などが一つのチームとなり顧問先企業をサポートする、日本で唯一の産業保健サービスが行える企業でございます。

略歴
2013年 旭川医科大学医学部医学科卒業、医師免許取得。
脳神経外科学、救急医学をベースに大学での臨床研究や多くの手術症例を経験。
より多くの人を幸せにするため2021年2月、株式会社NoLaBoを設立。
- 2021年8月 エターナルフィット西町南 開業
- 2022年11月 エターナルフィット厚別 開業
- 2024年7月 エターナルフィット円山 開業
- 救急科専門医
- 産業衛生専攻医
- 脳神経外科専門医
- 脳卒中専門医
- 脳血管内治療専門医
- 日本医師会認定健康スポーツ医
- 産業医
- 労働衛生コンサルタント
- 健康経営エキスパートアドバイザー
- 健康運動指導士
- 公認パーソナルトレーナー(NSCA-CSCS/CPT)
~お問い合わせ・資料請求について~
下記ボタンより、お問い合わせ・資料請求ができます。