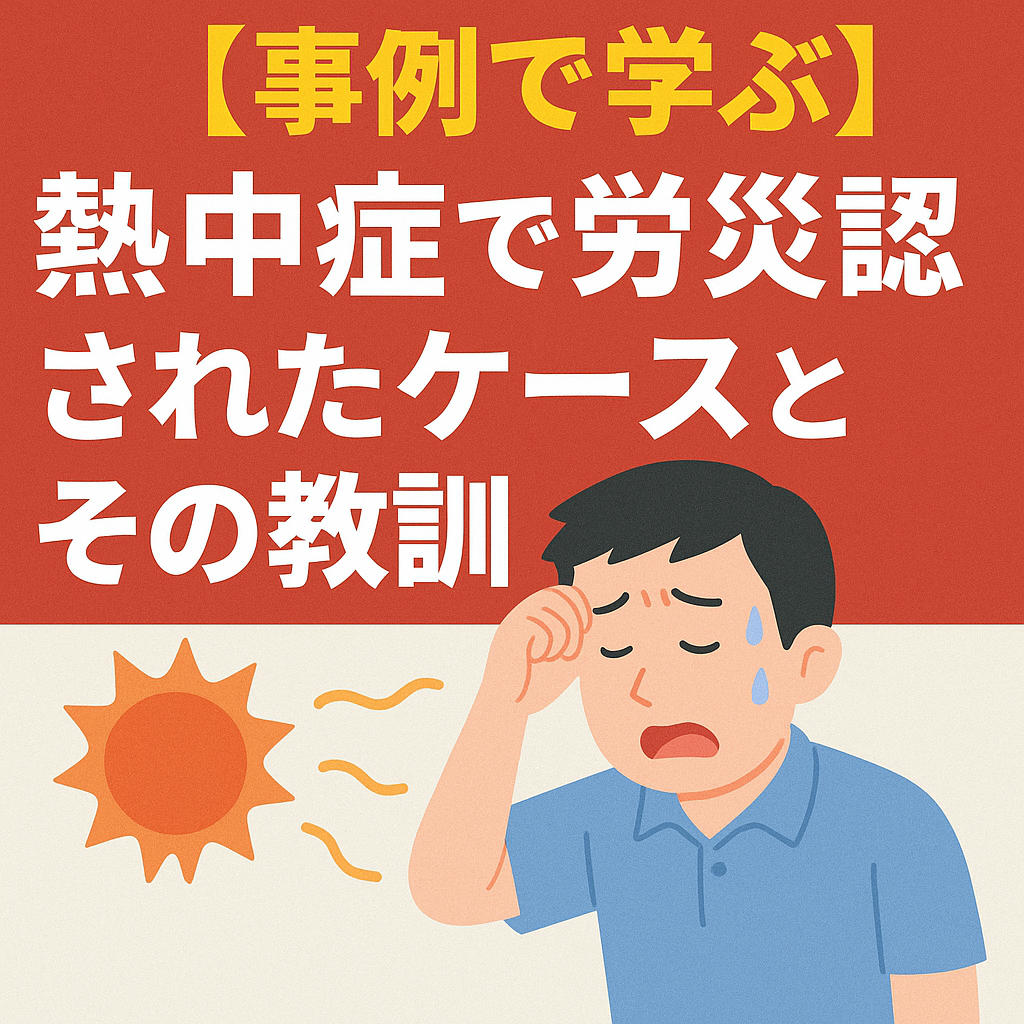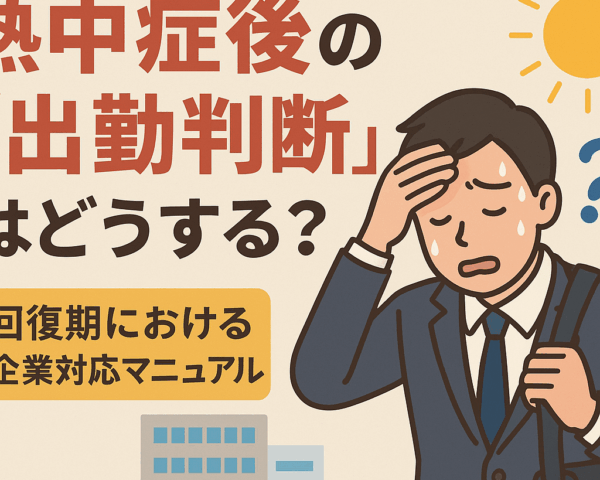目次
はじめに
近年、職場で熱中症により労災認定されるケースが増えています。厚生労働省の統計によれば、令和3年度には職場における熱中症による死亡者及び休業4日以上の疾病者が561人に上り、そのうち20人が死亡しています。本記事では、実際に労災認定された「熱中症事例」を取り上げ、事業者・労働者双方が学ぶべき教訓をまとめました。
熱中症で労災認定される要件とは?
労災認定の要件
熱中症が労災と認められるには、以下の2要件を満たす必要があります:
- 業務遂行性:業務中または通勤中に発症したこと
- 業務起因性:作業環境・作業内容が熱中症の原因であること
さらに認定では、「暑熱場所での業務と発症の因果関係が医学的にも明確であること」が求められます
労災認定されたケース集
ケース①:道路舗装工の死亡事例(2006年、東京地裁)
- 状況:道路舗装工が夏場の舗装作業中に心肺停止で死亡。🅰は軽度の基礎疾患があったが、汗まみれとなる過酷な作業環境だった。
- 裁判判断:業務による暑熱の影響と死亡との因果関係が認められ、労災と判定
教訓:長袖・長ズボンなどの作業着下で高温多湿な環境が継続する場合、作業中であっても「暑熱の業務」として労災になる可能性が高いです。
ケース②:造園業での死亡事例(大阪高裁 2016年)
- 状況:造園業の従業員が炎天下で庭木の伐採・清掃作業中に熱中症で死亡。体調不良を訴えていたが、適切な対応がされなかった。
- 裁判判断:熱中症に関する事業者への安全配慮義務違反が認められ、損害賠償責任が認定された
教訓:炎天下の作業で体調不良の徴候があれば、事業者は直ちに安全確保の措置を講じる義務があります。
ケース③:サウジアラビア出張中の死亡(福岡地裁小倉支部 令和6年)
- 状況:日本の企業が派遣した社員が、極端に暑いサウジアラビアでの作業中に熱中症により死亡。WBGTなど暑熱リスクの把握や救助体制が何ら整備されていなかった。
- 裁判判断:会社に安全配慮義務違反があると認定され、損害賠償責任が発生 。
教訓:高リスク地域での業務では、暑熱指数による環境管理やマニュアル・救護対応が必須です。
ケース④:造船・補修作業中の死亡(静岡地裁 2024年)
- 状況:30代男性が浚渫船の修理業務でサウジアラビアの炎天下作業中に死亡。暑熱対策が講じられず、企業に安全配慮義務違反が認定され、4800万円超の賠償命令が出た
教訓:海外での高温作業は国内以上の危険性があるため、企業は国際作業環境にも適切なマニュアル・対応体制を整備する必要があります。
ケース⑤:倉庫内の荷降ろし作業による死亡
- 状況:室内倉庫内ながら空調なし、WBGT測定なしでの荷降ろし作業後に熱中症による多臓器不全で死亡。
教訓:屋内でも暑熱リスクは無視できません。空調施設があっても、暑熱指数の把握・休憩管理が不十分なら隠れたリスクがある点に注意が必要です。
労災認定のポイントまとめ
- 暑熱環境の把握:WBGTなど暑さ指数による測定と記録
- 体調確認・水分補給・休憩管理の徹底
- マニュアル整備:発症時対応の明文化・周知
- 教育訓練:熱中症に関する衛生教育の実施
- 証拠収集:診断結果・気象情報・現場写真など、書類整備を用意
労災認定後の補償
認定されると以下の給付が受けられます:
- 医療費の全額補償
- 休業補償(平均賃金の60〜80%)
- 障害補償(後遺症が残った場合)
- 遺族補償(死亡時)
さらに、安全配慮義務違反が認定されれば、企業に対して損害賠償請求が可能です。
事業者に求められる対策と今後の方向性
■ 対策義務の強化(令和7年6月改正)
2025年6月の労働安全衛生規則改正で、熱中症予防のための体制整備・応急措置・報告体制などを事前に規定・周知することが法律上義務付けられました
■ 定期的な危険予知活動(KY活動)
現場単位で暑熱リスクを事前に確認し、対応策を話し合う習慣化が求められます。
■ データ活用・見える化
WBGT測定の結果や作業時間・休憩回数をデータ化し、管理者がリアルタイム把握できる仕組みづくりが有効です。
~熱中症労災を「防ぐ」ために~
労災として認定される熱中症は、単に暑いだけでなく、“予見可能で回避可能な事故”です。事業者は法令への対応だけでなく、日常的な危機管理として暑熱対策を徹底し、労働者の健康と命を守る責任があります。
本記事が、企業ご担当者・現場管理者・産業医・労働者にとって、熱中症対策と労災予防の一助となれば幸いです。
安全な職場環境の実現に向け、ぜひ自社での実践・改善をお進めください。
株式会社NoLaBoが提供する産業保健サービス
弊社はメディカルフィットネス事業と産業保健サービスを主軸にし、「健康と運動を通してたくさんの人を幸せにする」ための事業展開をしております。
厚生労働省認定のメディカルフィットネスで医学的な運動食事指導を、産業医、産業看護職、リハ職などが一つのチームとなり顧問先企業をサポートする、日本で唯一の産業保健サービスが行える企業でございます。

略歴
2013年 旭川医科大学医学部医学科卒業、医師免許取得。
脳神経外科学、救急医学をベースに大学での臨床研究や多くの手術症例を経験。
より多くの人を幸せにするため2021年2月、株式会社NoLaBoを設立。
- 2021年8月 エターナルフィット西町南 開業
- 2022年11月 エターナルフィット厚別 開業
- 2024年7月 エターナルフィット円山 開業
- 救急科専門医
- 産業衛生専攻医
- 脳神経外科専門医
- 脳卒中専門医
- 脳血管内治療専門医
- 日本医師会認定健康スポーツ医
- 産業医
- 労働衛生コンサルタント
- 健康経営エキスパートアドバイザー
- 健康運動指導士
- 公認パーソナルトレーナー(NSCA-CSCS/CPT)
~お問い合わせ・資料請求について~
下記ボタンより、お問い合わせ・資料請求ができます。