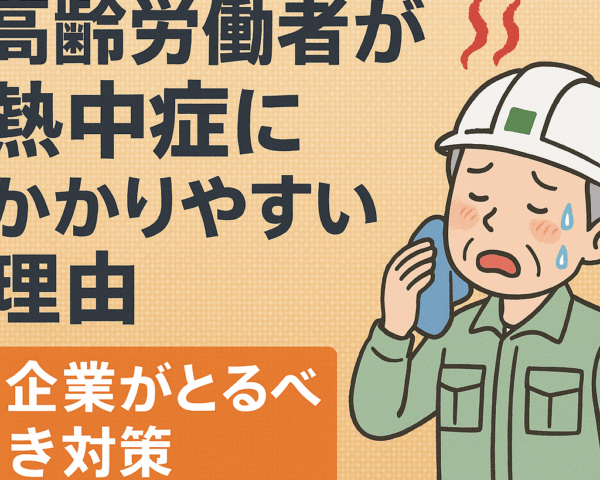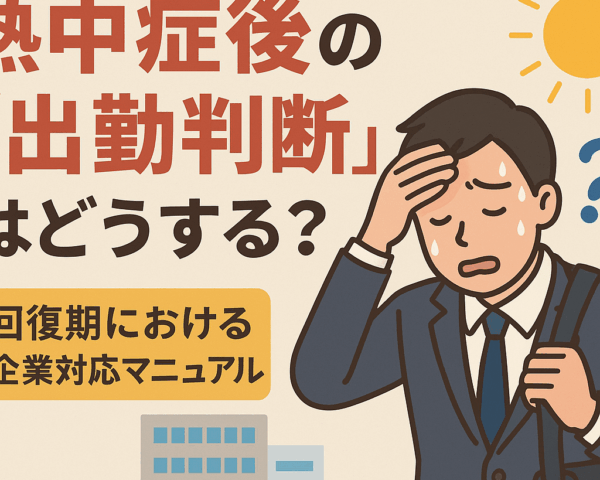目次
「かくれ脱水」とは?
「かくれ脱水」とは、脱水の自覚症状が無いまま進行する状態で、現場では「だるい」「集中できない」といった漠然とした不調として現れます。自覚に乏しい分、放置されがちですが、作業効率低下や熱中症危険度上昇の要因です
現場で見抜く“8つのサイン”
①ベタつき(首や背中)
蒸し暑さ+不快感、実は皮膚表面に水分が残っている証。
②全身のだるさ・倦怠感
作業強度に見合わない疲労は、血液循環の悪化を示唆します。
③フラツキ・頭くらくら
血液が濃くなることでめまいや立ちくらみが生じます。
④痛み・こむら返り・頭痛
電解質不足により筋肉が攣りやすく、頭痛も現れやすくなります。
⑤口の渇き・粘つき
のどの渇きは遅れて現れる症状。粘ついた口内はすでに脱水傾向。
⑥尿量減少・着色尿
濃い黄色~茶色の尿は明らかな警告。1500mL前後の水分排出が目安
⑦皮膚のハリ低下(つまみテスト)
爪を押す・皮膚をつまむなどでチェック。戻りに3秒以上かかると危険信号
⑧注意散漫・判断力低下
0.1%でも水分失うと集中力や反応が鈍るとされています
現場でできる簡易セルフチェック
✔ 爪圧迫テスト
親指の爪を押し、白くなった色の戻りを1〜2秒以内で確認。3秒以上で要注意
✔ 皮膚つまみテスト
皮膚を軽くつまんで離し、戻り具合を確認。3秒以上残ると脱水疑い
これだけで現場でも簡単・頻繁にチェックが可能です。
脱水 vs 熱中症:認識と対応の違い
脱水はあくまで体内水分減少、熱中症はその延長線上。
軽い脱水状態が進むと熱中症Ⅰ度(だるさ・頭痛)→Ⅱ度(吐き気・意識障害)→Ⅲ度(けいれん・意識消失)へ急変する恐れがあります
判断力低下や作業ミスを引き起こす前段階で食い止めることが重要です。
5%未満の水分不足でも軽視できない理由
わずか1〜2%の脱水でも注意散漫・反応鈍化が起こり、作業ミスや事故のリスクが高まります。
5〜6%の水分不足で筋肉けいれん、集中力低下、尿回数減少が起こり、10〜15%失うと幻覚・意識障害・死に至るリスクも。
予防策:水・塩分・休憩・環境整備
①水分と電解質の補給
OSHA/NIOSHは“20分ごとにコップ1杯”(約240ml)の水分補給を推奨。2時間以上なら電解質飲料も必要
また、水だけでなく塩分・ナトリウム・カリウムなどが含まれた飲料を併用するのが効果的。
②こまめな休憩と休憩施設
暑熱度が高いときは、クーリングブレイクや影のある休憩スペースの確保が不可欠です。
③工学的・行政的対策
送風ファン、ミスト、陰に作業場所を配置、熱アラートの発令など。熱ストレスのモニタリングも導入推奨。
④教育とコミュニケーション
「のどが渇く前に飲む」「疲れに気づいたら申告」「爪・皮膚チェックを励行」などの安全教育が重要。
現場での具体的運用例
- 朝礼時に「今日の水分」宣言:「60分毎に水1杯」等の目標を共有
- チェックリスト配布:「ベタっ/だるっ/フラっ/いたっ」4点セットを記名式で毎勤務記入
- 爪チェック付シフト表活用:「白から戻る時間を記録して脱水改善を意識付け」
- 水飲みステーション常設:容易に飲める位置に水・経口補水液・スポーツドリンクを常備
- 送風ファン+日陰設置:風通しを良くし、こまぎれな休憩環境の整備
まとめ
- 「かくれ脱水」は気づかれないまま進行し、事故や熱中症へつながる
- 爪圧迫・皮膚つまみ・4語サインなど、現場で簡単にセルフチェック可能
- 予防には水・電解質のこまめ補給、教育、休憩環境の整備が必須