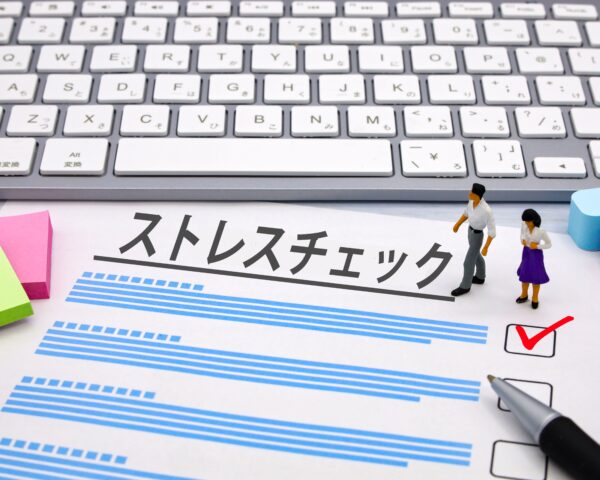目次
なぜ今「高ストレス者対応」が重要なのか?
職場におけるメンタルヘルス不調は、現代社会で深刻な課題となっています。過重労働、人間関係、業績プレッシャーなど、ストレスの要因は多岐にわたります。
企業は「ストレスチェック制度」を通じて従業員のメンタル状況を把握し、特に「高ストレス」と判定された従業員には早期に適切な対応を行うことが求められます。これは単なる健康管理の一環ではなく、従業員の離職防止、生産性向上、企業イメージの保全という点でも重要です。
本記事では、高ストレス者への対応方法を具体的なステップに分け、産業医や人事担当者の視点から実践的に解説していきます。
高ストレス判定とは?ストレスチェック制度の基本
ストレスチェック制度は、2015年12月より労働安全衛生法に基づいて義務化された制度で、常時50人以上の労働者がいる事業場に対して年1回の実施が求められます。
この制度では、従業員に対し質問票(職業性ストレス簡易調査票など)を用いてストレスの程度を評価し、「高ストレス」と判定された場合、以下の対応が推奨されます。
- 本人への結果通知
- 本人の希望があれば医師による面接指導
- 面接指導に基づく企業側の職場改善
高ストレス判定は、「メンタル不調予備軍」とも言え、早期対応を行わなければ、休職や退職、さらには労災請求に発展するリスクもあるため、企業は真摯な対応が求められます。
高ストレス者への企業の正しい対応ステップ
ステップ1:結果の通知とプライバシー保護
まず重要なのは、本人に結果を丁寧に通知すること。通知の際は、プライバシーへの最大限の配慮が不可欠です。
- 結果は本人に直接、個別に通知
- 同意なしに上司や他の社員に共有しない
- 結果内容を元に評価・査定などを行わない
この段階で信頼関係を損なうと、面接指導の受診率が低下し、制度そのものが形骸化する恐れがあります。
ステップ2:面接指導の勧奨と産業医の活用
本人が希望した場合、産業医による面接指導が実施されます。ここで企業が注意すべき点は、「面接指導を強制しない」こと。
面接指導を受けやすくするための工夫:
- 面接日時・場所の柔軟な設定
- 費用負担の明確化(企業負担であることの説明)
- 信頼できる医師の選定と紹介
面接では、ストレスの要因が職場か私生活かを見極め、必要に応じて職場改善提案がなされます。
ステップ3:職場環境の見直しと改善提案
面接指導の結果、職場に起因するストレス要因(上司との関係、業務過多、評価制度など)が明らかになった場合、企業は速やかに対応する責任があります。
例:
- 一時的な業務量の軽減
- 部署変更・配置転換
- コミュニケーション研修の導入
特に、同様のストレス要因が複数名に見られる場合は、職場全体の構造的な課題として改善に取り組むことが必要です。
ステップ4:継続的なフォローアップと再発防止
面接指導後であっても、対応は一度で終わりではありません。
- 状況の変化を定期的にヒアリング
- 必要に応じて再面談
- 回復が確認されるまで支援を継続
さらに、再発を防ぐためには、メンタルヘルス教育の全社的な推進や、定期的なストレスチェックの質向上など、組織ぐるみの取り組みが求められます。
注意点と企業が陥りやすいNG対応
やってはいけない対応例:
- 面接を拒否した社員への圧力
- 高ストレス判定者の「監視」や「評価対象化」
- 産業医の報告を無視して何もしない
ストレスチェックは、あくまで「予防ツール」であり、従業員を責めるためのものではありません。信頼関係のない対応は、離職やメンタル疾患の深刻化を招くだけです。
また、制度導入の目的は、「社員の健康保持と職場環境の改善」にあります。企業の責任として、制度を形だけで終わらせず、真摯な対応を継続する姿勢が重要です。
まとめ:対応力が企業の信頼を高める
ストレスチェックで高ストレスと判定された社員への対応は、企業の「人を大切にする姿勢」が問われる場面です。
- プライバシーへの配慮
- 医師との連携
- 環境改善の実行力
- 継続的な支援体制の整備
これらの対応を誠実に行うことは、単に社員の健康を守るだけでなく、職場の信頼感や働きやすさを向上させ、優秀な人材の定着にもつながります。
企業が本気で取り組むべきテーマであり、「対応力=企業力」と言っても過言ではありません。今後もメンタルヘルスを重視する時代において、制度を最大限に活かすことが求められています。
株式会社NoLaBoが提供する産業保健サービス
弊社はメディカルフィットネス事業と産業保健サービスを主軸にし、「健康と運動を通してたくさんの人を幸せにする」ための事業展開をしております。
厚生労働省認定のメディカルフィットネスで医学的な運動食事指導を、産業医、産業看護職、リハ職などが一つのチームとなり顧問先企業をサポートする、日本で唯一の産業保健サービスが行える企業でございます。

略歴
2013年 旭川医科大学医学部医学科卒業、医師免許取得。
脳神経外科学、救急医学をベースに大学での臨床研究や多くの手術症例を経験。
より多くの人を幸せにするため2021年2月、株式会社NoLaBoを設立。
- 2021年8月 エターナルフィット西町南 開業
- 2022年11月 エターナルフィット厚別 開業
- 2024年7月 エターナルフィット円山 開業
- 救急科専門医
- 産業衛生専攻医
- 脳神経外科専門医
- 脳卒中専門医
- 脳血管内治療専門医
- 日本医師会認定健康スポーツ医
- 産業医
- 労働衛生コンサルタント
- 健康経営エキスパートアドバイザー
- 健康運動指導士
- 公認パーソナルトレーナー(NSCA-CSCS/CPT)
~お問い合わせ・資料請求について~
下記ボタンより、お問い合わせ・資料請求ができます。